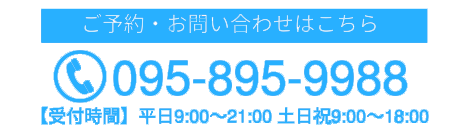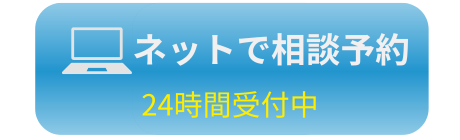調停・裁判に関するQ&A

調停・裁判に関するQ&A
【弁護士が解説】離婚調停に欠席し続けたらどうなる?無断欠席を続けた場合の結末
「離婚調停を申し立てたのに、相手が一度も裁判所に来ない。」、「仕事の都合で、どうしても調停期日に出席できそうにない」
家事調停(離婚、婚姻費用、面会交流など)を進める中で、当事者の欠席は珍しいことではありません。
しかし、相手に無視され続けたり、ご自身が出席できなかったりする場合、「このまま調停はどうなってしまうのだろうか」と大きな不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。 この記事では、家事調停の当事者が欠席を続けた場合に法的に何が起こるのか、申立人側・相手方側それぞれの立場から、弁護士が分かりやすく解説します。

Question&Answer
【Question】
家事調停(離婚調停、婚姻費用調停、面会交流調停など)に当事者が欠席する場合どうなる?
【Answer】
調停を申し立てられた相手方が欠席を続ける場合、調停成立の見込みがないものとして調停が不成立となり、調停の対象により自動的に審判に移行する場合と、別途訴訟提起が必要になる場合とがあります。
一方、調停の申立て人が欠席を続ける場合、調停委員会の判断で、家事事件手続法271条に基づき調停事件が終了となる可能性もあります。
1 【結論】異議申立てで調停は終了。次は「審判」か「訴訟」
「調停を無視しても、特に罰則はないのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、それは間違いです。
家庭裁判所から呼出しを受けたにもかかわらず、正当な理由なく調停を欠席すると5万円以下の過料に処せられることになります(家事事件手続法258条1項、51条)。
裁判所から期日通知書を受領した後に調停に欠席したら過料に処せられる?
家事調停事件においては、調停を申し立てられた相手方には期日通知書という書類が届きます。
この期日通知書が「呼出し」にあたるのであれば、期日通知書を受領した後に無断で調停に欠席すると過料に処せられる可能性があります。
この点については、期日に出頭しない当事者に対し法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を課すには「呼出状の送達」または「出頭したものに対する期日の告知」の方法による「呼出し」が必要とされています(家事事件手続法34条4項、民事訴訟法94条2項)。
そのため、期日通知書を受領した後に調停期日に無断欠席したとしても、そのことのみをもって過料に処せられるということはありません。
とはいえ、これは決して欠席を推奨するものではありません。
無断欠席を続ければ、裁判所はより強制力のある「呼出状」の送達といった手続きに移行する可能性があり、最終的に過料のリスクが生じます。
また、何より裁判所に不誠実な印象を与え、心証を悪くするおそれがありますので、裁判所からの通知には誠実に対応することが重要です。
2 相手方(申し立てられた側)が欠席し続けたらどうなる?
2.1 結論:調停は「不成立」で終了する
家事調停の相手方(調停を申し立てられた側)が家事調停に欠席を続ける場合、「当事者間に合意が成立する見込みがない」(家事事件手続法272条1項)として、調停が不成立となります。
2.2 調停不成立後の流れ
調停が不成立となった場合、調停の対象である事項に応じて、自動的に次のステップに進むか、ご自身で新たな手続きを取る必要があります(家事事件手続法272条3項、4項)。
・自動的に「審判手続」へ移行するケース
対象:婚姻費用、面会交流、遺産分割など
概要:家事事件手続法別表第2の事項
・ご自身で「訴訟」を提起する必要があるケース
対象:離婚、離縁など
概要: 家事事件手続法別表第2以外の事項
3 申立人(申し立てた側)が家事調停に欠席を続けたらどうなる?
申立人が(調停を申し立てた側)が家事調停に欠席を続ける場合、相手方が欠席する場合と同様に「当事者間に合意が成立する見込みがない」として調停が不成立になりそうです。
しかし、相手方が欠席を続ける場合と異なり、申立人が欠席を続ける場合、申立人は家事調停の申立てにより実現しようとした内容についてもはや関心を喪失している可能性があります。
とくに家事調停のうち、別表第2の事項については調停が不成立になると自動的に審判に移行するところ、申立人が欠席を続けるような場合にも調停を不成立とした上、審判手続に移行すべきなのかという点には疑問が生じます。
実際、民事訴訟の場合、原告が訴訟に欠席を続ける場合には訴えの取下げを擬制する規定が存在します(民事訴訟法263条)。
家事調停においては、このような訴えの取下げを擬制する規定は存在しないものの、申立人が欠席を続ける場合には、調停委員会が家事事件手続法271条に基づき調停事件を終了させることが可能ということになっています。
4 (補足)審判手続に移行した後に申立人が欠席し続けた場合はどうなる?
では、審判手続に移行した後に申立人が欠席し続けた場合はどうなるのでしょうか。
このような場合、民事訴訟と同様に申立ての取下げが擬制されます(家事事件手続法83条)。
5 【対処法】どうしても調停に出席できない場合
「仕事がどうしても休めない。」、「相手と同じ建物内にいるのが精神的に苦痛だ。」といった理由で、調停への出席が困難な場合もあるかと思います。
その場合は、弁護士に代理人を依頼することをご検討ください。
弁護士に依頼すれば、ご本人が裁判所に出向かなくても、代理人として弁護士が期日に出席し、あなたの代わりに主張や交渉を行うことができます。
無断欠席でリスクを負う前に、まずは弁護士に代理人を依頼できないか相談してみることをお勧めいたします。
※本記事では「家事調停(離婚調停、婚姻費用調停、面会交流調停など)に当事者が欠席を続ける場合どうなるか?」について解説いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。
そこで、離婚問題についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めいたします。
家事事件手続法第258条(家事審判の手続の規定の準用等)
1 第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。
家事事件手続法第51条(事件の関係人の呼出し)
1 家庭裁判所は、家事審判の手続の期日に事件の関係人を呼び出すことができる。
2 呼出しを受けた事件の関係人は、家事審判の手続の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。
3 前項の事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、五万円以下の過料に処する。
家事事件手続法第34条(期日及び期間)
4 民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、家事事件の手続の期日及び期間について準用する。
民事訴訟法第94条(期日の呼出し)
1 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
家事事件手続法第272条(調停の不成立の場合の事件の終了)
1 調停委員会は、当事者間に合意(第二百七十七条第一項第一号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。ただし、家庭裁判所が第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により家事調停事件が終了したときは、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
4 第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。
民事訴訟法第263条(訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
家事事件手続法第83条(家事審判の申立ての取下げの擬制)
家事審判の申立人(第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合にあっては、当事者双方)が、連続して二回、呼出しを受けた家事審判の手続の期日に出頭せず、又は呼出しを受けた家事審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは、家庭裁判所は、申立ての取下げがあったものとみなすことができる。