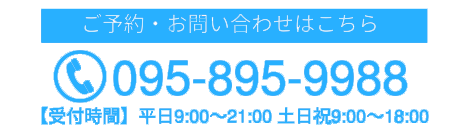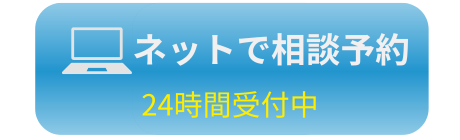調停・裁判に関するQ&A

調停・裁判に関するQ&A
【弁護士が解説】「調停に代わる審判」に異議を申し立てたらどうなる?調停は再開せず次のステップへ移行します
家庭裁判所から「調停に代わる審判」が届き、「内容に納得できないけれど、異議を申し立てるとどうなるのだろう?」と不安に思っていませんか?
「また調停がやり直しになるの?」、「いきなり裁判になってしまうの?」
この記事を読めば、異議申立て後の正確な手続きの流れと、損をしないための注意点が分かります。
この記事でわかること
・異議申立てをすると、調停は再開されず終了する
・その後の手続きは、自動的に「審判」へ移行するケースと、新たに「訴訟」を起こす必要があるケースの2つに分かれる
・異議申立て後に取るべき行動と注意点

1 【結論】異議申立てで調停は終了。次は「審判」か「訴訟」
1.1 (前提)異議申立てを行わなかった場合
調停に代わる審判に異議申立てがなされなかった場合や異議申立てを却下する審判が確定した場合、審判の内容に応じて確定した家事審判や確定判決と同一の効力を有することになります(家事事件手続法287条)。
1.2 異議申立てを行った場合
【異議申立て後の流れ早わかり】
→審判は効力を失い、調停は終了します。
・対象が財産分与、養育費、遺産分割などの場合
→ 自動的に「審判」手続きへ移行
・対象が離婚、離縁などの場合
→ 手続きは一旦終了 → 解決には「訴訟」を新たに起こす必要あり
調停に代わる審判に対して異議申立てを行った場合、適法な異議申立てとして審判が効力を失うと、家事調停事件は異議申立てのあった日に完結するとされています(松川正毅=本間靖規=西岡清一郎編『新基本法コンメンタール人事訴訟法・家事事件手続法【第2版】』689頁参照)
その後、家事事件手続法別表第2(婚姻費用、財産分与、遺産分割など)の事項については、家事調停の申立ての時に、家事審判の申立てがあったものとみなされ、自動的に審判手続へ移行することとなります(家事事件手続法286条7項)。
一方、離婚や離縁など別表第2以外の事項については、審判に移行することがないため、紛争解決のためには別途訴訟提起する必要があります(家事事件手続法286条6項参照)。
2 異議申立ての基本|期限・方法・理由
2.1 ポイント1:期限は「告知を受けてから2週間以内」
異議申立ては、調停に代わる審判の告知を受けた日から2週間以内に、当事者が行う必要があります(家事事件手続法286条1項、2項、279条2項、3項)。
家庭裁判所は、異議申立権のある者による異議申立てか、異議申立期間内になされた異議申立てかを審査した上、不適法な申立てについては却下することとなります(家事事件手続法286条3項)。
2.2 ポイント2:方法は「書面」の提出
異議申立ては、「書面」で行う必要があります(家事事件手続規則138条1項)。
2.3 ポイント3:理由は不要
後記「調停に代わる審判の告知は公示送達できない」のとおり、調停に代わる審判は、当事者が異議申立てを行わないという消極的態度をもって当事者間に事後的な同意があったものと考える制度です。
そのため、審判の内容に納得できない場合には理由を述べることなく異議申立てを行うことが可能です。
3 異議申立て後の注意点
3.1 審判に移行した場合:調停の資料は引き継がれる
調停に代わる審判に異議申立てを行ったことにより家事調停が審判手続へ移行した場合、家庭裁判所は、審判手続の中で事実の調査及び証拠調べを行うことにより調停段階で提出された資料を審判資料とすることが可能です(家事事件手続法56条参照)。
そのため、調停段階で提出した資料は、審判における資料になると考えておく必要があります。
なお、調停が審判に移行する際に追加で印紙を納める必要はありません。
3.2 訴訟を提起する場合:2週間以内の訴訟提起にはメリットあり
離婚や離縁など別表第2以外の事項について、調停に代わる審判に異議申立てを行った場合、訴訟での解決を目指す場合には2週間以内に訴訟提起すると以下のメリットがあります。
①調停申立て時と訴訟提起時のずれによる不利益を避けることができる
2週間以内に訴訟提起すると、調停申立て時に訴え提起があったものとみなされる(家事事件手続法286条6項)ため、訴え提起時を基準にすると消滅時効が完成しているなどの不利益を回避することが可能です。
具体的には、婚約破棄の損害賠償請求や親族間での貸金返還請求等について家事調停の申立てを行った場合などに問題となります。
②手数料(印紙代)が無駄にならない
2週間以内に訴訟提起した場合、調停申立ての際に裁判所へ納めた手数料(印紙代)が、訴訟を起こす際の手数料から差し引かれるため、手数料(印紙代)が無駄になりません(民事訴訟費用等に関する法律5条1項)。
そのため、調停に代わる審判に対し異議申立てを行った場合において、当事者が訴訟により解決を目指すのであれば、異議申立ての通知を受けた日から2週間以内に訴訟提起すると手数料の面でメリットがあります。
ただし、民事調停の場合に調停を求める事項の価額に応じて手数料が異なるのとは違い、家事調停の手数料は定額(1,200円)であるため、金銭的なメリットは限定的ではあります。
離婚調停などの家事調停ではなく、民事調停の場合には、「調停に代わる審判」と類似する調停に代わる決定(17条決定)がなされる場合があります。
調停に代わる決定(17条決定)については、詳しくは以下のページをご参照ください。
関連記事:17条決定に異議申立てを行うとどうなる?調停終了と訴訟移行を弁護士が解説
4 そもそも「調停に代わる審判」とは?
調停に代わる審判とは、家事調停が成立しない場合において、家庭裁判所が職権ですることができる審判です(家事事件手続法284条1項)。
実務的には、当事者間で離婚や離縁について合意できているものの当事者が期日に出頭できない場合(離婚及び離縁については当事者の出頭がなければ調停を成立させることができないため)、当事者の一方が欠席を続けており調停での解決が望めない場合、当事者間で合意はできないものの意見の相違が僅かであるため家庭裁判所の審判により終局的に解決できる可能性がある場合などに調停に代わる審判が利用されています。
合意に相当する審判の対象事件については調停に代わる審判はできない
婚姻の無効や取消し、縁組の無効や取消し、認知や認知の無効、取消しなどについては、合意に相当する審判の対象事件とされています(家事事件手続法277条1項)。
合意に相当する審判は、公益性が高いことから任意処分が許されず、本来、人事訴訟の手続によって審理判断されるべき事項について、一定の要件のもとに簡易迅速に処理することを認めた制度であるとされています。
そのため、合意に相当する審判の対象事件については、審判を受けることの合意を慎重に確認する必要があるとして、調停に代わる審判の対象外とされています(金子修編著『逐条解説 家事事件手続法〔第2版〕』976頁、1002頁参照)。
調停に代わる審判の告知は公示送達できない
調停に代わる審判は、「相当と認める方法で告知」されることとされていますが(家事事件手続法258条1項、74条1項)、異議申立期間との関係で送達手続が取られるのが通例です。
しかし、調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によって行うことはできません(家事事件手続法285条2項)。
これは、調停に代わる審判は、当事者が異議申立てを行わないという消極的態度をもって当事者間に事後的な同意があったものと考える制度(金子修編著『逐条解説 家事事件手続法〔第2版〕』1007頁参照)であるところ、当事者の異議申立権を実質的に奪うおそれのある公示送達による告知は認めないこととしたものです。
公示送達できない結果、調停に代わる審判の告知ができない場合、家庭裁判所は調停に代わる審判を取り消した(家事事件手続法285条3項)上、「当事者間に合意が成立する見込みがない」(家事事件手続法272条1項)として調停が不成立とすることになります。
※本記事では「調停に代わる審判へ異議申立てを行うと調停が再開するのか?」について解説いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。
そこで、離婚問題についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。
家事事件手続法第56条(事実の調査及び証拠調べ等)
1 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。
2 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。
家事事件手続法第74条(審判の告知及び効力の発生等)
1 審判は、特別の定めがある場合を除き、当事者及び利害関係参加人並びにこれらの者以外の審判を受ける者に対し、相当と認める方法で告知しなければならない。
2 審判(申立てを却下する審判を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、審判を受ける者(審判を受ける者が数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによってその効力を生ずる。ただし、即時抗告をすることができる審判は、確定しなければその効力を生じない。
3 申立てを却下する審判は、申立人に告知することによってその効力を生ずる。
4 審判は、即時抗告の期間の満了前には確定しないものとする。
5 審判の確定は、前項の期間内にした即時抗告の提起により、遮断される。
家事事件手続法第258条(家事審判の手続の規定の準用等)
1 第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。
家事事件手続法第272条(調停の不成立の場合の事件の終了)
1 調停委員会は、当事者間に合意(第二百七十七条第一項第一号の合意を含む。)が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、家事調停事件を終了させることができる。ただし、家庭裁判所が第二百八十四条第一項の規定による調停に代わる審判をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定により家事調停事件が終了したときは、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
4 第一項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停事件が終了した場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。
家事事件手続法第279条(異議の申立て)
1 当事者及び利害関係人は、合意に相当する審判に対し、家庭裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、当事者にあっては、第二百七十七条第一項各号に掲げる要件に該当しないことを理由とする場合に限る。
2 前項の規定による異議の申立ては、二週間の不変期間内にしなければならない。
3 前項の期間は、異議の申立てをすることができる者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては当事者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。
4 第一項の規定による異議の申立てをする権利は、放棄することができる。
家事事件手続法第285条(調停に代わる審判の特則)
1 家事調停の申立ての取下げは、第二百七十三条第一項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない。
2 調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。
3 調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。
家事事件手続法第286条(異議の申立て等)
1 当事者は、調停に代わる審判に対し、家庭裁判所に異議を申し立てることができる。
2 第二百七十九条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による異議の申立てについて準用する。
3 家庭裁判所は、第一項の規定による異議の申立てが不適法であるときは、これを却下しなければならない。
4 異議の申立人は、前項の規定により異議の申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
5 適法な異議の申立てがあったときは、調停に代わる審判は、その効力を失う。この場合においては、家庭裁判所は、当事者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 当事者が前項の規定による通知を受けた日から二週間以内に家事調停の申立てがあった事件について訴えを提起したときは、家事調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。
7 第五項の規定により別表第二に掲げる事項についての調停に代わる審判が効力を失った場合には、家事調停の申立ての時に、当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなす。
8 当事者が、申立てに係る家事調停(離婚又は離縁についての家事調停を除く。)の手続において、調停に代わる審判に服する旨の共同の申出をしたときは、第一項の規定は、適用しない。
9 前項の共同の申出は、書面でしなければならない。
10 当事者は、調停に代わる審判の告知前に限り、第八項の共同の申出を撤回することができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
家事事件手続法第287条(調停に代わる審判の効力)
前条第一項の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判が確定したときは、別表第二に掲げる事項についての調停に代わる審判は確定した第三十九条の規定による審判と同一の効力を、その余の調停に代わる審判は確定判決と同一の効力を有する。
家事事件手続規則第138条(異議の申立ての方式等・法第二百八十六条)
1 法第二百八十六条第一項の規定による異議の申立ては、書面でしなければならない。