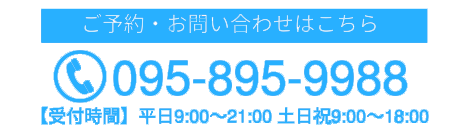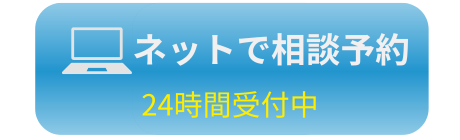離婚の成立に関する事例

離婚の成立に関する事例
【所在不明の夫と離婚成立】定年退職後に連絡がつかない夫と離婚できた事例
ご相談者Pさん
ご相談者様:Pさん(女性・主婦)
ご相談内容:夫と離婚したい
相手方:夫(無職・所在不明)
解決方法;裁判

※案件や依頼者様の特定ができないように内容を編集しております。
状況
Pさんは、夫の過去の不倫やお金遣いの荒さに長年苦しみながらも、お子様のことを思い、離婚を思いとどまってきました。
しかし、夫の単身赴任が終わり、定年退職して家に戻ってくる可能性が浮上。「これ以上一緒に生活することはできない」と、Pさんは同居を拒否しました。
すると、夫は定年退職後、連絡が取れず行方も分からない状態に(夫の住民票はPさん宅に残ったままでした)。
Pさんは、浪費癖のある夫が退職金を全て使ってしまうのではないかと強い不安を覚え、離婚と財産分与の問題について当事務所の弁護士にご依頼されました。
弁護士の活動
1 夫の財産を保全!迅速な「預貯金の仮差押え」
まず最優先したのは、夫が退職金を使い込んでしまうことを防ぐことでした。
弁護士は、Pさんからお話を伺い、夫の退職金が振り込まれた可能性の高い口座に見当をつけ、速やかに裁判所へ仮差押命令の申立てを行いました。
その結果、夫が受領したと見込まれる退職金の半額に相当する預貯金の仮差押えに成功しました。
これにより、離婚成立前に夫が勝手に財産を処分してしまうリスクを回避しました。
なお、最終的に、訴訟終了後、仮差押えを本差押えに移行するなどして、約1200万円を獲得することができました。
預貯金の仮差押えと強制執行については、別途以下のページでまとめていますので、ご覧ください。
関連記事:【離婚時の財産分与】夫の預貯金仮差押えで確保した解決事例
2 行方不明の夫へのアプローチ:あらゆる手段で接触を試みる
次に、離婚に向けた話し合いのため、夫の住所を把握する必要がありました。
弁護士は、Pさんからお聞きした情報をもとに、夫に何度も電話を試みましたが、応答はありませんでした。
そこで、「夫が子どもに対し、自分宛の郵便物を実家に送るよう指示」していたことを踏まえ、夫の実家住所宛に「離婚協議申入書」を送付しました。
しかし、それでも夫からの連絡はなく、依然として行方不明の状態が続きました。
3 「離婚調停」への移行
夫と連絡を取れないことから、法的な手続きを進める必要がありました。
弁護士は、夫が郵便物の送付先として指定していた実家住所を夫の住所として、家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
しかし、夫は調停にも参加しなかったため、このまま調停を続けても進展は見込めないと判断し、初回の調停期日で調停不成立として終了させました。
4 夫の住所等が不明でも離婚を可能に:「公示送達」による離婚裁判の提起
調停が不成立となってから1か月以内に、弁護士は、夫の住所等が不明であるとして「公示送達」を前提に離婚裁判を提起しました。
「公示送達」とは、相手の住所等が不明な場合に、裁判所の掲示板などに一定期間所定の掲示することで、相手に訴状等が届いたものとみなす法的手続きです。
裁判所からは、夫の実家の状況について追加調査を求められましたが、弁護士が電話等で夫が実家に居住していないことを確認し、調査報告書にまとめて提出しました。
その結果、公示送達が認められ、夫が裁判に出席しないまま、Pさんの主張と証拠に基づいて裁判を進めることができました。
最終的に、財産分与、慰謝料等で合計約1200万円の支払いを命じる判決を獲得した上、無事、離婚も成立しました。
ポイント
今回のケースのように、相手が行方不明であったり、話し合いに全く応じない場合でも、適切な法的手続きを踏むことで離婚や財産分与を実現できる可能性があります。
1 相手が話し合いに応じない場合の「離婚調停」の進め方
離婚調停はあくまで裁判所で行う話合いの手続であるため、当事者双方が離婚に合意しない限り離婚は成立しません。
そのため、相手方が出席しない場合や離婚に合意する見込みがない場合には、調停を長引かせても時間だけが過ぎてしまいます。
本件のように、相手が調停に参加しないことが予想される場合は、早期に調停を不成立とし、次のステップである「離婚裁判」に移行する判断が重要です。
これにより、解決までの時間を短縮できます。
2 行方不明の相手と法的手続きを進めるための「公示送達」
相手の居場所が分からない場合でも、諦める必要はありません。「公示送達」という制度を利用すれば、相手が裁判に出席しなくても裁判を進めることができます。
ただし、裁判所に公示送達を行ってもらうには原則として当事者の申立てが必要(民事訴訟法110条)ですが、申立てに際し、「住所、居所その他送達をすべき場所が知れない」ことに関する調査報告書の提出が求められます。
求められる調査の内容は事案により異なりますが、今回のケースでは、夫住民票上の住所がPさんの住所と同一の住所であり、夫の住所が住民票上の住所と一致していないことは明らかであったため、夫が郵便物の送付先として指定した実家住所についての調査が求められました。
民事執行法110条
1 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
① 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
② 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
③ 外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
④ 第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。
3 「公示送達」による離婚裁判でも、主張と証拠の準備が不可欠
離婚裁判においては、夫の不貞行為や財産分与、婚姻費用の未払分の清算等を求め、主張立証を行いました。
公示送達を前提とする離婚裁判の場合、相手方が裁判に参加しない可能性が高く、原告の主張立証のみを基礎として判決が出ることになるのが通常です。
ただし、擬制自白は成立しないため、十分に証拠を収集しておく必要があります。
関連記事:擬制自白とは?裁判で不利にならないための基礎知識を弁護士が解説
最後に
Pさんのように、相手が行方不明になってしまった、話し合いに全く応じてくれないといった困難な状況でも、弁護士が法的な手続きを適切に進めることで、離婚を成立させ、正当な権利を実現できる可能性があります。
「もう無理かもしれない…」と諦めてしまう前に、ぜひ一度、弁護士へご相談ください。
※掲載中の解決事例は、当事務所で御依頼をお受けした事例及び当事務所に所属する弁護士が過去に取り扱った事例について、案件や依頼者様の特定ができないように内容を編集したものです。